良質な睡眠をとりましょう
良質な睡眠には、量(時間)、質(休養感)が重要です
睡眠は最も重要な休養行動です。
睡眠時間は長すぎても短すぎても健康を害する原因となり、朝目覚めた時に感じる休まった感覚(睡眠休養感)は良い睡眠の目安となります。
例えば、日中にしっかりからだを動かし、夜は暗く静かな環境で休むといった、寝て起きてのメリハリをつけることは、睡眠休養感を高めることに役立ちます。
睡眠時間を確保し、睡眠休養感を高める工夫を日常生活に取り入れましょう。

よりよい睡眠をとるために
環境づくり
光の環境づくり
- 起床後に朝日の強い光を浴びることで、体内時計はリセットされ睡眠リズムを整えることができます。
- 日中に光を多く浴びることで、睡眠リズムを整える「メラトニン」というホルモンが夜間に多く分泌されるようになります。すると、スムーズな入眠、良質な睡眠につながります。
- 夜に強い光を浴びることは睡眠の妨げになります。スマートフォンやタブレット端末を寝室には持ち込まないようにしましょう。
温度の環境づくり
- 寝室は暑すぎず寒すぎない、心地よい温度を心がけましょう。就寝の約1~2時間前に入浴し体を温めると入眠しやすくなります。
音の環境づくり
- 騒音は眠りの質を下げる原因になります。騒音が気になる場合は、カーテンを防音機能があるものに変えたり、窓から離れて眠ることも有効です。
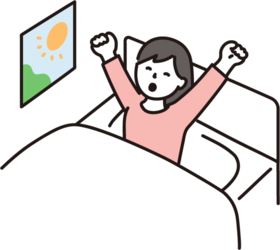
生活習慣と睡眠
適度な運動習慣を身につける
適度な運動習慣を身につける睡眠は、日中の身体活動等で消耗した体力等の回復の役割も担うことから、「日中どのくらい活動したか」が、眠りの必要量や質に影響します。
おすすめの運動
- ウォーキングのような有酸素運動
- ダンベルを使うような筋力トレーニング ※息が弾み、汗をかく程度
おすすめのタイミング
日中の運動がおすすめですが、夕方や夜の時間帯でも睡眠改善に効果があると報告されています。(目安:就寝の約2~4時間前まで)
しっかり朝食を摂り、夜食を控える
朝食を抜くと体内時計が乱れ、睡眠不足や休養感の低下につながります。
また、就寝前の夜食や間食も体内時計を狂わせ、睡眠の質を下げる原因になります。
リラックスが大事
スムーズに眠るためには、寝る1時間前から家事や勉強を控え、リラックスして脳を落ち着かせることが大切です。
入眠を促すリラックス法
- 瞑想法
- 静かに行うヨガ
- 腹式呼吸
- 音楽
- アロマ

寝る前の嗜好品は控えよう
日常生活の中で習慣的に摂取する嗜好品の中には、睡眠に影響を及ぼすものがあります。
カフェイン
カフェインは覚醒作用があるため、寝つきの悪化や中途覚醒の増加、眠りの質を低下させる恐れがあります。
1日の摂取量は、400ミリグラムを超えないようにしましょう。
400ミリグラム未満であっても、夕方以降のカフェインの摂取は睡眠に影響するため控えましょう。
アルコール
アルコールは一時的には寝つきを良くし、睡眠前半では深い睡眠を増加させます。しかし、睡眠後半の眠りの質は著しく悪化し、飲酒量が増えるにつれて中途覚醒の回数も増えることが報告されています。
ニコチン
たばこに含まれるニコチンは覚醒作用があり、睡眠前の喫煙は、寝つきの悪化、中途覚醒の増加、睡眠の質の低下をもたらします。
子どもから高齢者までみんなのGood Sleepガイド
厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業)「適切な睡眠・休養促進に寄与する「新・健康づくりのための睡眠指針」と連動した行動・習慣改善ツール開発及び環境整備」研究班(研究代表者 栗山健一 国立精神神経医療研究センター)において作成された「Good Sleepガイド(ぐっすりガイド)」では、「健康づくりのための睡眠ガイド2023」に基づき、成人・子ども・高齢者向けにわかりやすく良い睡眠のポイントをまとめています。
-
Good Sleepガイド(ぐっすりガイド)成人版 (PDF 1008.4KB)

-
Good Sleepガイド(ぐっすりガイド)こども版 (PDF 1.0MB)

-
Good Sleepガイド(ぐっすりガイド)高齢者版 (PDF 990.9KB)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

